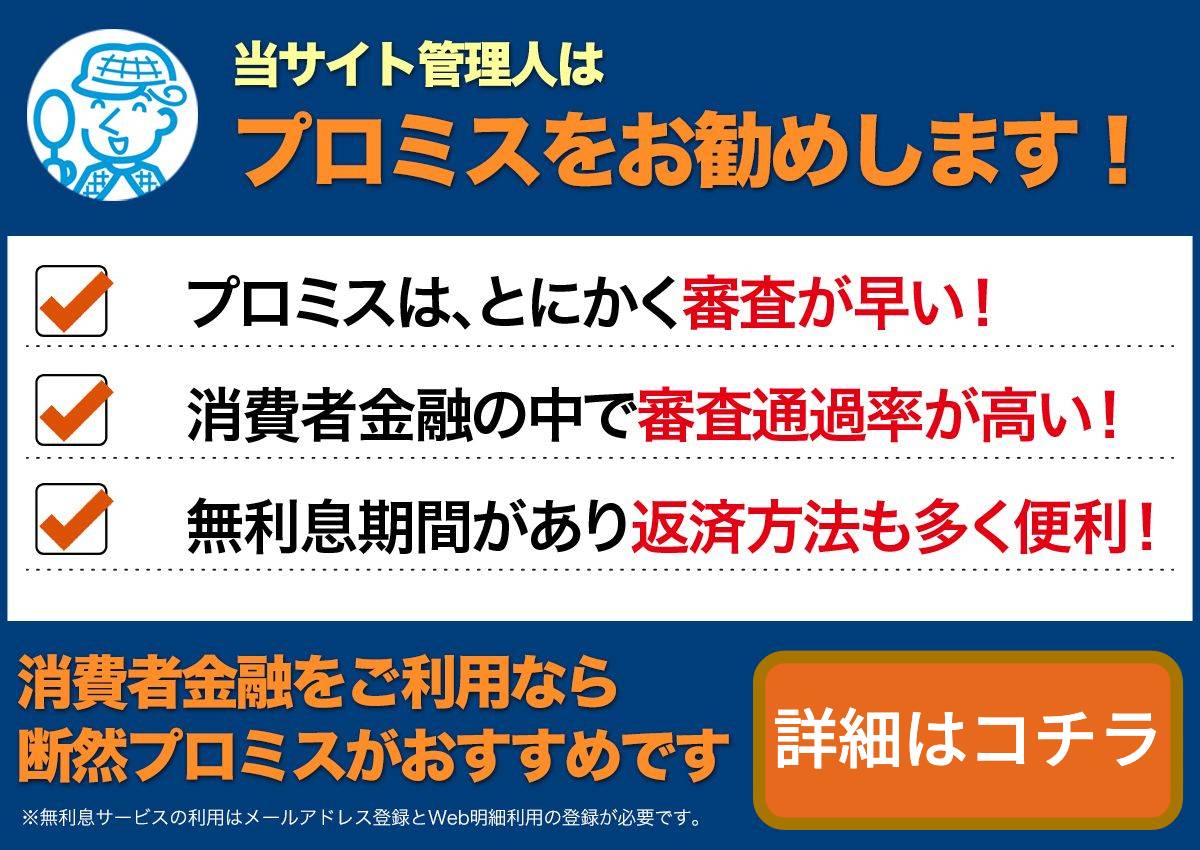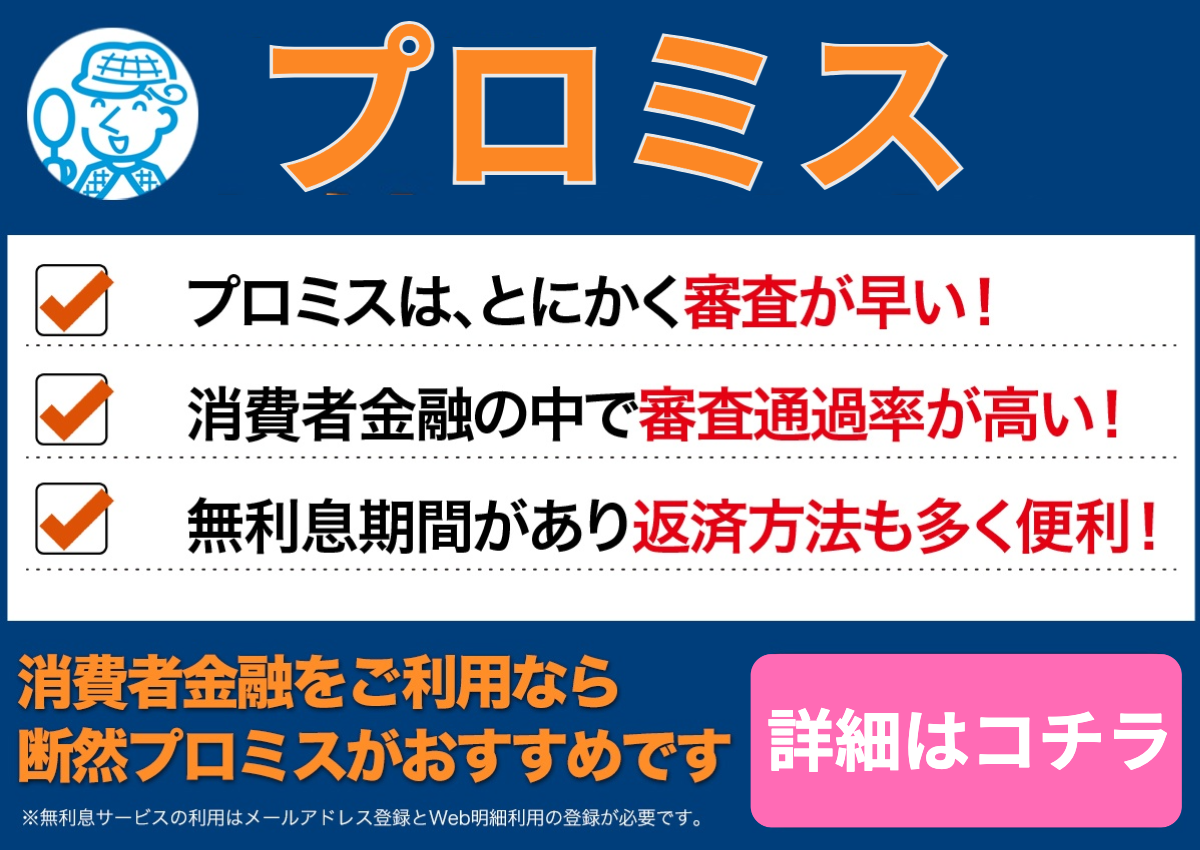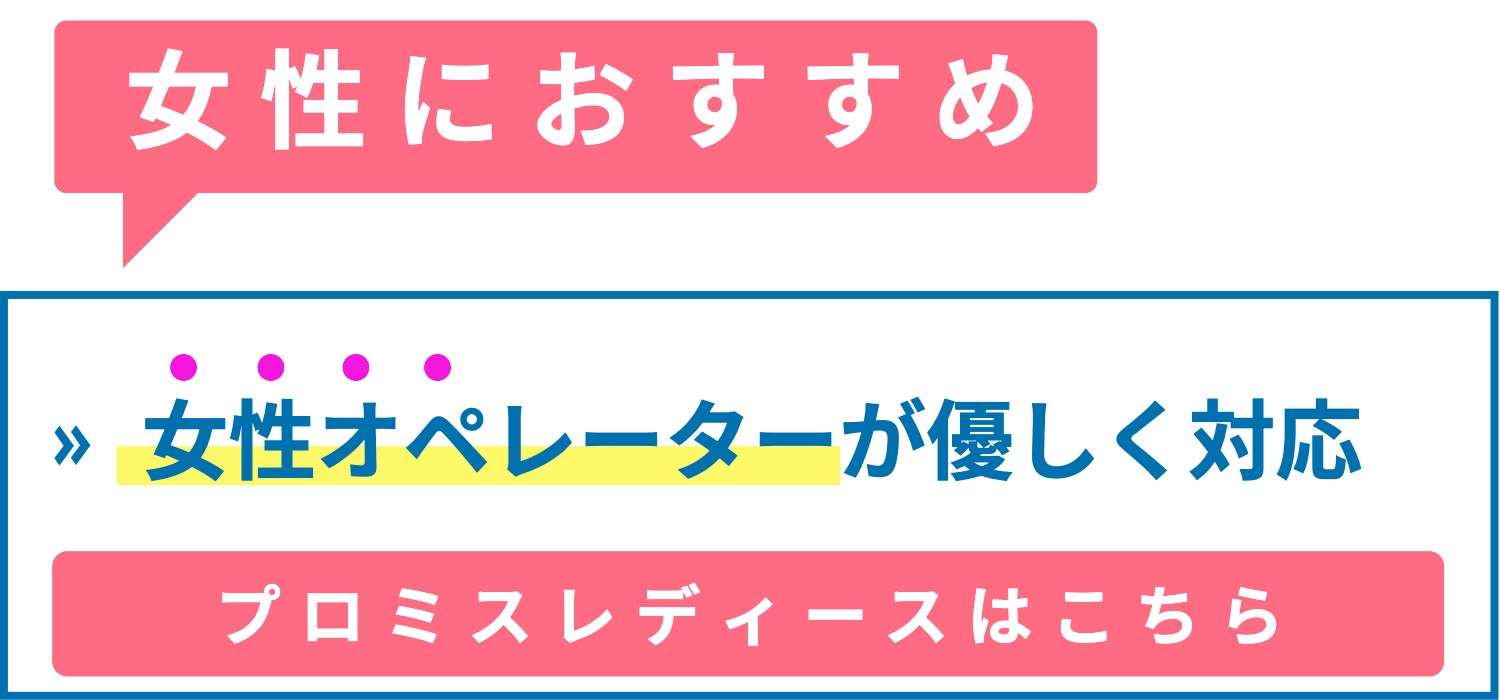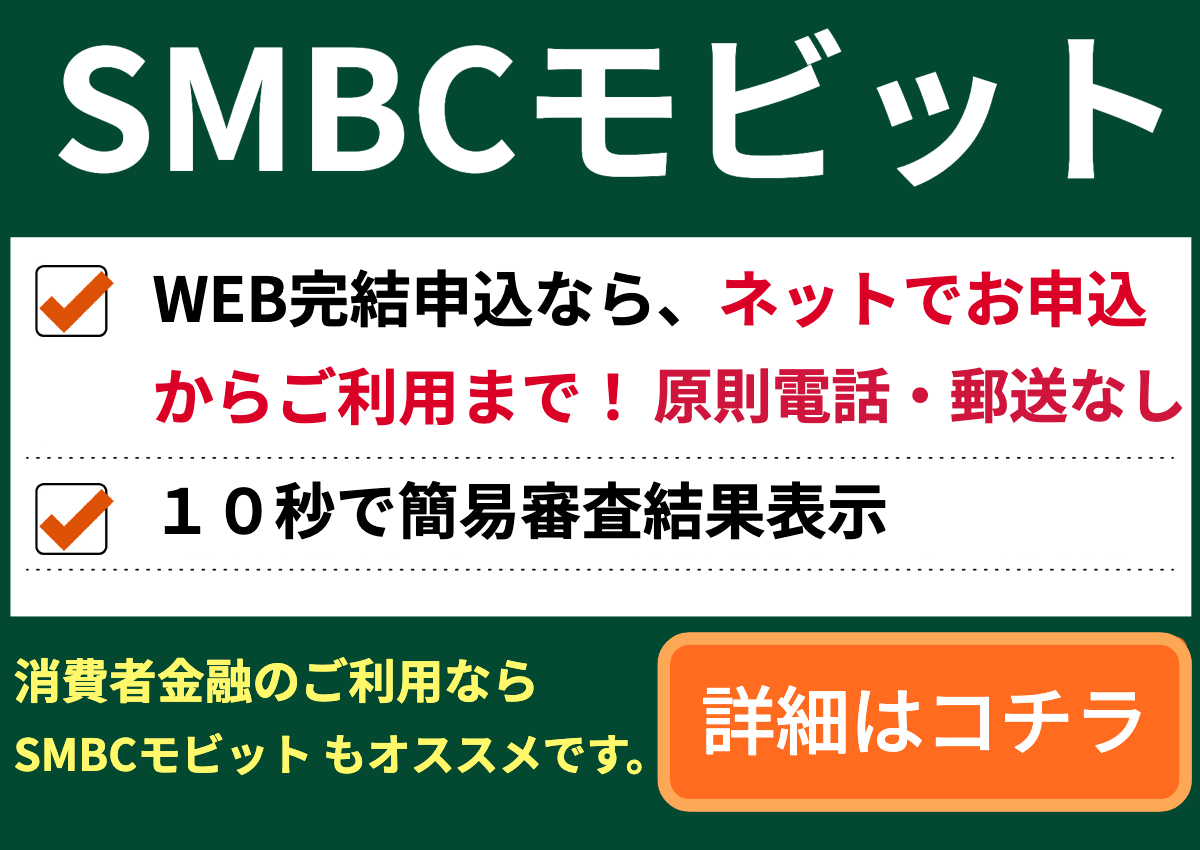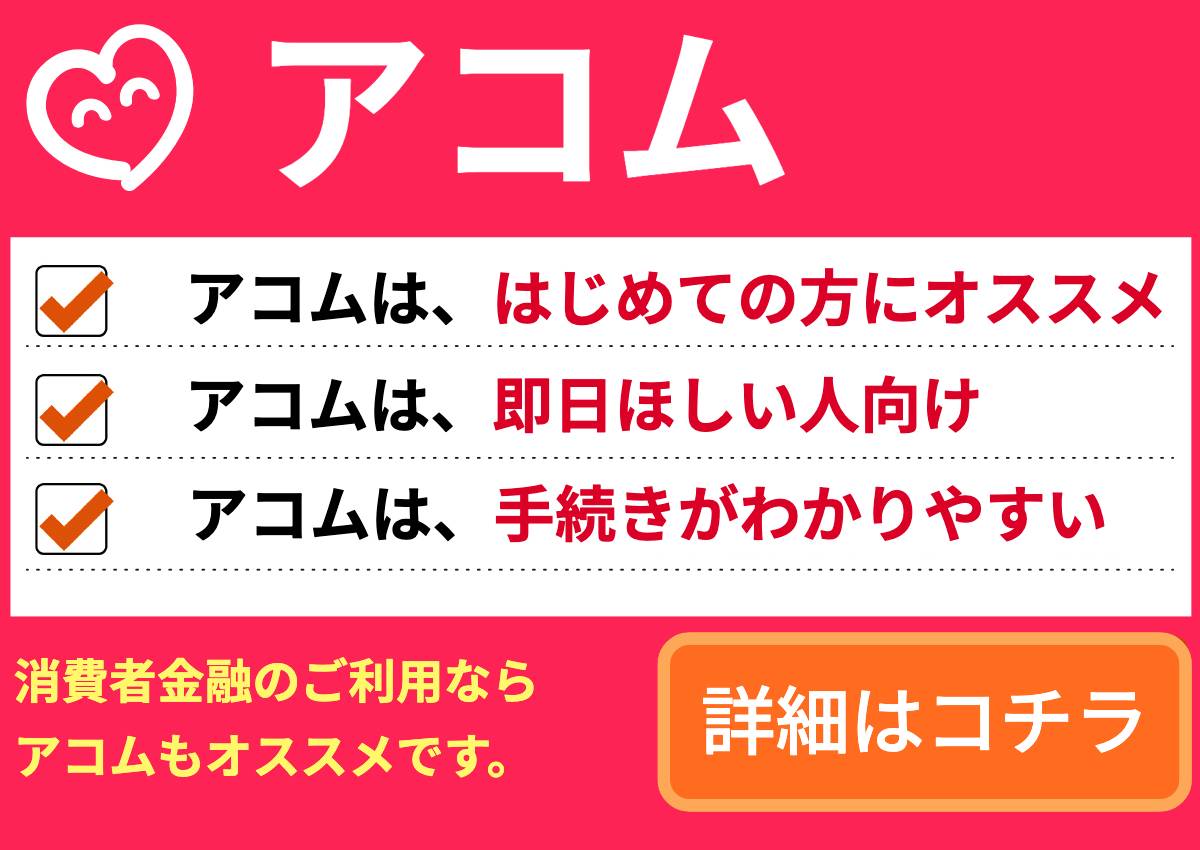※当サイトはプロモーションが含まれています

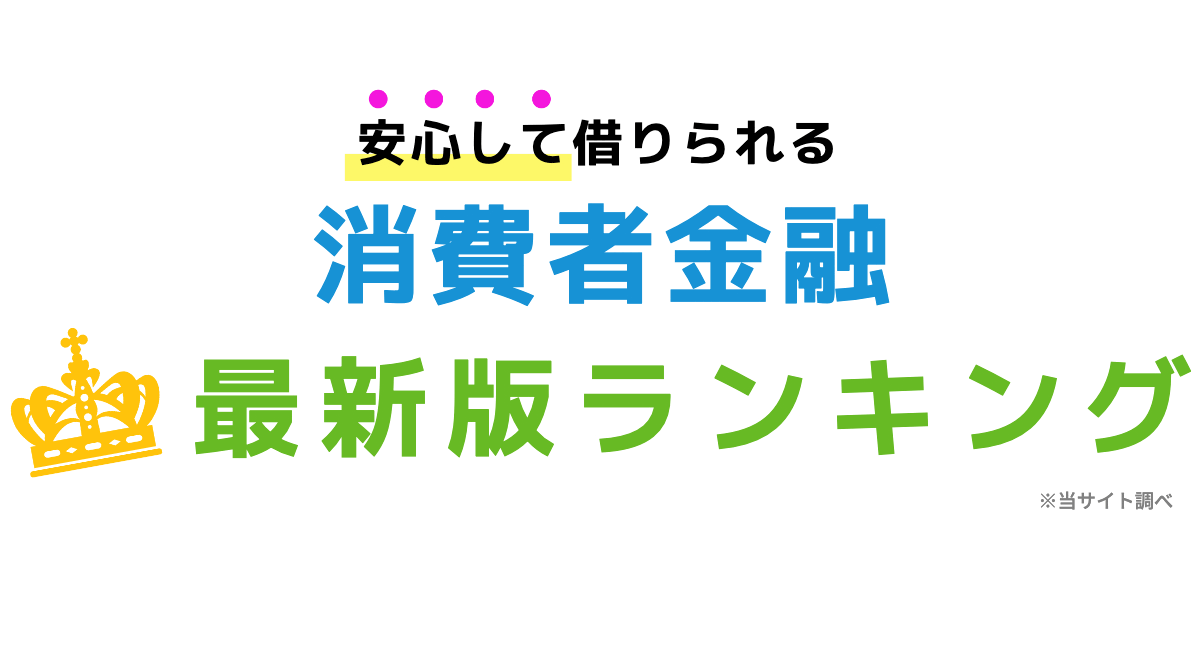
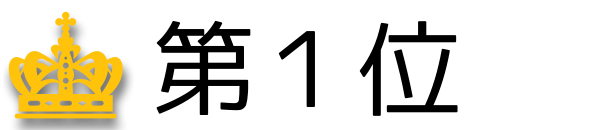
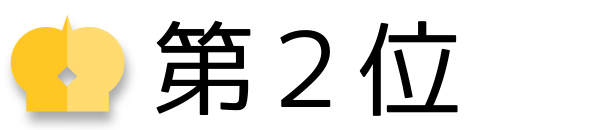
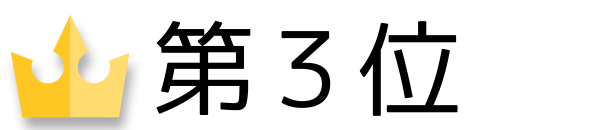
キャッシングのメリットについて
キャッシングは、急な出費や予期せぬ支出に対応するための手段として、多くの消費者に利用されています。以下に、キャッシングのメリットについて詳しく説明します。
1. 簡便な申し込み手続き
キャッシングの申し込み手続きは、インターネットやスマートフォンから簡単に行うことができます。従来の銀行ローンと比較して、必要な書類や審査項目が少なく、手続き自体も迅速です。
2. 迅速な審査と即日融資
一般的に、キャッシングの審査は迅速であり、申し込みから数時間以内に審査結果が通知されることがあります。審査に合格した場合、即日融資が可能なことが多いため、急な資金需要にも迅速に対応できます。
3. 柔軟な返済プラン
キャッシングでは、返済プランが柔軟であることが特長です。一般的に、短期間の融資から長期の分割払いまで、様々な返済オプションが用意されています。利用者のニーズや状況に合わせて、適切な返済プランを選択することが可能です。
4. リボ払いやボーナス払いなどの特典
一部のキャッシングサービスでは、リボ払いやボーナス払いなどの特典が用意されています。リボ払いでは、毎月の支払額を柔軟に調整できるため、急な支出に対応しやすくなります。ボーナス払いでは、ボーナスを受け取った際に一部を返済に充てることができ、無理なく借り入れを返済できる利点があります。
5. クレジットカードとの連携
一部のキャッシングサービスでは、クレジットカードとの連携が可能です。これにより、クレジットカードの利用限度額を超えた場合でも、キャッシングを利用することで緊急の資金調達が可能となります。また、クレジットカードと同様にポイントや特典が付与される場合もあります。
6. 安心の利用環境
多くの消費者金融が信頼性の高いサービスを提供しており、適切な利用環境を提供しています。情報漏洩や不正利用への対策が強化されており、利用者のプライバシーやセキュリティを保護する取り組みが行われています。
7. 信用情報への影響が比較的少ない
キャッシングの利用は、一般的に銀行のカードローンやクレジットカードと異なり、信用情報への影響が比較的少ないとされています。そのため、一時的な資金需要に対応する際に、将来の信用に影響を及ぼすことが少ない利点があります。
まとめ
キャッシングは、急な資金需要に迅速に対応するための有効な手段として利用されています。簡便な申し込み手続きや迅速な審査、柔軟な返済プランなど、様々なメリットがあります。ただし、利用時には適切な計画と責任ある返済が重要です。